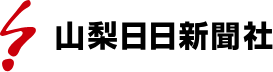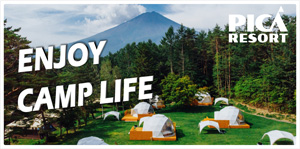弾丸登山抑止
弾丸登山とは、夜間に富士山5合目に到着し、御来光を見ようと睡眠をとらずに一気に山頂を目指す、0泊2日の登山行程。
弾丸登山は、睡眠不足や体が高地に慣れないことによって、体調を崩しやすいとされ、不慮の事故につながる危険性が指摘されている。特に酸素が薄く、気温の変化が激しい富士山では、高山病を発症したり、夜明け前の頂上付近での登下山道の渋滞も深刻化していて、落石や将棋倒しで大事故になる可能性が大きい。
実際、2013年シーズン中における富士山7合目救護所の受診状況で、弾丸登山とみられる人の受診割合が、それ以外の登山者の1.4倍余りに上った。また、弾丸登山が高山病の高い発症率に影響しているとみられる調査結果もある。
山梨、静岡両県など地元自治体は2013年から、観光庁をはじめ、旅行業協会や大手旅行会社、登山用品店などに、弾丸登山自粛の協力を要請。また、6合目安全指導センターや5合目などに、4カ国語で弾丸登山の自粛を訴える看板を設置。さらに「富士山における適正利用推進協議会」が同年7月に制定した『富士登山における安全確保のためのガイドライン』に、遭難・事故のリスク情報のひとつとして弾丸登山を盛り込んだ。加えて2014年登山シーズンからは、富士山有料道路(富士スバルライン)のマイカー規制期間を過去最長の53日間とし、シャトルバスの夜間運行本数を減便するなどの対応をした。2017年にはマイカー規制期間をさらに63日間に延長した。
その結果、吉田口登山道における、登山者全体に対する弾丸登山者の割合(開山期間中)は年々減少し、2017年は前年比0.79ポイント減の6.99%(1万5636人)で、5年連続で前年を下回った。2018年は7.15%と微増も、弾丸登山者数は1万4067人と減少。全登山者数が前年より12.1%減少したことが要因と考えられる。
2022年は2954人で、登山者全体の2.57%。2021年の2.47%より微増だが、2019年の5.98%からは大きく下がった。富士山有料道路(富士スバルライン)の営業時間の短縮や危険性を訴える周知活動が低水準につながったとみている(山梨県富士吉田市調べ)。
◇
2023年6月、新型コロナウイルスの感染症法の位置づけが5類に移行して初めて迎える富士山の夏山シーズンを前に、「弾丸登山」による事故の増加が懸念されるとして、富士北麓の6市町村長と富士山吉田口旅館組合の組合長らが、登山者数の制限を求める要望書を山梨県に提出。要望書では、県に対して、登山者が集中した時間帯に時限的な入山規制を行うなどの対応を提案。県の主導で国や地元市町村、関係機関などと協議を始めるよう促した。吉田口登山道沿いの山小屋では5月以降、宿泊予約が殺到。地元市町村などは、山小屋に泊まれない人らが夜間に一気に山頂を目指す「弾丸登山」が増え、傷病や落石などのリスクが高まると危惧している。要望書では「富士登山の価値や世界文化遺産登録10周年に沸く機運を大きく損なう」と指摘している。
また山梨県が、登山者に対する安全登山を呼びかける巡回指導の体制を拡充。巡回指導は7月15日~9月10日のうち、特に弾丸登山による混雑が予想される毎週金曜日の深夜から土曜日の早朝にかけて実施。2人1組で登山道を巡回し、急いで登ったり、前方の人を追い越したりしないよう、安全な登山を呼びかける。