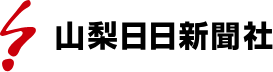炎の帯 夜空を焦がす 吉田の火祭り

国道139号を照らす大たいまつの明かり=富士吉田市内(2024年)

御旅所に入る明神神輿=富士吉田市内(2024年)
400年以上続く伝統行事「吉田の火祭り」が26、27の両日、富士吉田市上吉田の北口本宮冨士浅間神社などで開かれる。静岡県の「島田帯祭」、愛知県の「国府宮はだか祭り」と並び、日本三奇祭の一つと称され、国の重要無形民俗文化財にも指定されている。大たいまつが国道139号などに並び、富士北麓に夏の終わりを告げる。
祭りは26日午後2時半、北口本宮冨士浅間神社で行われる「手水の儀」で幕を開ける。本殿祭、諏訪神社祭を経て、同5時ごろには「明神神輿」と富士山をかたどった「おやま神輿」の2基が出発する。
神輿は国道139号(富士みち)などを練り歩き、上吉田コミュニティセンターに設けられた「御旅所」に到着。「御旅所着輿祭」を開き、同6時半ごろに大たいまつの点火が始まる。
たいまつは、国道139号の約2キロの区間に100本以上が並べられる。かつて数多くの富士講信者が宿泊した「御師のまち」は炎の帯によって赤く照らされて、幻想的な雰囲気に包まれていく。例年、市民や富士講信者、観光客らが夜空を焦がす炎を眺めながら、過ぎゆく夏を惜しむ。
本祭りとなる27日の「すすき祭り」では、2基の神輿が午後2時に、安置していた御旅所から北口本宮冨士浅間神社へ向けて出発。市内を練り歩き、同7時ごろ、神社内にある諏訪神社に到着。神輿が「高天原」と呼ばれる場所を周回し、祭りは最高潮を迎える。
神輿の担ぎ手だけではなく、参拝者らも周回の輪に加わる。ススキの玉串を持って神輿の後に続くことで、防火や安全、商売繁盛、学業成就の願いがかなうとされている。
(2025年8月26日付 山梨日日新聞掲載)