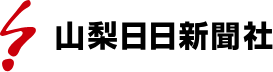サイト内検索結果
山梨県富士吉田市上吉田の北口本宮冨士浅間神社を起点とする吉田口登山道を富士に向かって約3キロ、諏訪の上から遊境下へ進み左に分岐して約1キロ行くと泉瑞(別称泉津湖)に出る。泉瑞には、源頼朝にまつわる伝説が残っている。 …
山梨県は世界文化遺産登録の富士山をはじめ、ユネスコエコパークに登録された南アルプス、八ケ岳など高山・名山が多い。これらの山々の中から、古里の自然、文化、歴史の豊かさ再発見を目的に1997年2月に県が選定した「山梨百名山…
忍野村忍草の新名庄川沿いでは、ソメイヨシノが満開を迎えた。 村の観光名所「忍野八海」から徒歩約5分の場所にあるお宮橋では、富士山とサクラの共演を楽しもうと、連日多くの観光客がカメラを構えている。 16日までの日没~…
都留市桂町の宝鏡寺(佐藤宏俊住職)で、県自然記念物のヤマブキソウが見頃を迎え、訪れる人の目を楽しませている。 寺によると、ヤマブキソウはケシ科の多年草で、境内の斜面に群生。今年は例年より2週間ほど早い4…
天下茶屋は富士河口湖町の国道137号の新御坂トンネル近くのバス停「三ツ峠入り口」から県道708号を車で約15分、旧御坂トンネル南側の出入り口近くにある。 建てられたのは1934(昭和9)年の秋。現在のものは3代目で1…
富士河口湖町河口の河口湖北岸では約200本のソメイヨシノが満開となり、多くの観光客が訪れている。 同所では16日まで、富士・河口湖さくら祭り(同実行委主催)が開かれている。日没~午後9時はライトアップが実施され、多く…
山梨県富士吉田市と山中湖村を結ぶ国道138号に隣接する小立の中にある「鐘山の滝」。富士吉田市と忍野村の境界付近。国道からは約100メートル近さ。別名「小佐野の滝」とも呼ばれる。 山中湖を水源とする桂川が溶岩で覆われた…
都留市金井の桂林寺(織田宗覚住職)で、境内のソメイヨシノとシダレモモが見頃を迎え、ピンクの花々の共演が訪れる人を楽しませている。 境内にはソメイヨシノ8本とシダレモモ約20本が植えられていている。いずれも例年より1週…
山梨県道志村には源頼朝が弓矢で打ち抜いたとされる岩「的様」の伝説が残っている。 道志村の伝説には源頼朝にまつわる伝説や旧跡が数多く残されているが、頼朝が富士の巻き狩りの折、この地を武道練成の場として一の的、二の的、三…
見頃を迎えた西願寺(都留市上谷6丁目)のシダレザクラ。隣に植えられたモミジは毎年春になると新芽が赤く色づくことから、「七変化モミジ」として市民に親しまれている。大江信彦住職は「サクラとモミジの共演を楽しんでほしい」と話…
山梨県富士山世界文化遺産保存活用推進協議会が進める「富士講」をテーマにした誘客プロジェクト。世界文化遺産としての富士山の価値をPRし、通年型の観光振興につなげるのが狙い。 吉田口登山道などを登るモニターツアーを開いた…
1週間分の備蓄求める 富士山火山防災対策協議会は富士山噴火に備える避難基本計画の最終報告で大規模降灰時の対応を初めて示し、住民は自宅などの屋内に退避することを原則とした。事前に食料やヘルメットなどの備蓄品を用意しておき…
「蒼竜峡」は、山梨県都留市十日市場の蒼竜峡団地から富士急行線十日市場駅にかけての約1.2キロの桂川渓谷を指す。 桂川の激流により、両岸の溶岩が浸食され、まるで魚のうろこのような岩肌になっており、岩と岩の間を水が流れる…
富士山麓の医療機関対応に限界 行政の手厚い支援を 3月29日に公表された富士山噴火の避難基本計画の最終報告では、3時間以内に溶岩流の到達が予想される医療機関や福祉施設で、入院患者や入所者らの避難策を検討するよう求めた。…
都留市の鹿留川が流れる周辺に「住吉七景」がある。このひとつがおなん淵(ふち)。深さ約5メートルで、高さ約6メートルの滝もあり滝の裏側には岩が柱のように立っている柱状節理がある。 伝説によると、この淵近くの長者の家に奉…
富士山研・吉本主幹研究員に聞く 富士山噴火に備えた避難基本計画の最終報告が公表されたことを受け、富士山科学研究所の吉本充宏主幹研究員に、観光客や要支援者に避難してもらう際のポイント、自治体や住民に求めることなどを聞いた…
小林萬吾(1870-1947年)は香川県に生まれ、漢学を修めた後、松山の官立中学に入学。このころ、洋画家の原田直次郎(1863-1899年)に師事し、後に明治の洋画壇の第一人者であった黒田清輝(1866-1924年)が…
富士山 外国人対応は未定 富士山火山防災対策協議会が避難基本計画の最終報告をまとめ、噴火警戒レベルの早い段階から、登山者に下山と帰宅を促す方針を示した。一方で、外国人登山者に特化した項目はなく、地元市町村が山小屋関係者…
白瀧幾之助(1873-1960年)は兵庫県の出身。小学校を卒業後、工学士を夢見て上京するが、洋画家、山本芳翠(1850-1906年)との出会いによって洋画家を志し、山本が主宰する生巧館画塾や、黒田清輝(1866-192…
富士吉田 技術生かし染め直しも 富士吉田市上暮地の染色加工業「丸幸産業」(堀内茂利社長)がアパレルブランド「ROUNDHAPPY」を立ち上げた。半世紀にわたって織物の街で培った染色技術を残し、発信していこうと初めてブラ…
外務省が、新たな日本国旅券(パスポート)に、葛飾北斎の浮世絵「冨嶽三十六景」のデザインを採用。 旅券デザインに採用されるのは24作品で、いずれも山梨県立博物館の収蔵品から採用。同館がシリーズ全46作を一括所蔵、いずれも…
富士河口湖町の小中学校11校と鳴沢村の鳴沢小で行われている富士山学習の成果が、同町船津の河口湖ショッピングセンターBELLで、展示された。 町地域防災課によると、町内の小中学校は毎年、各学校で富士山に関する学習を実施…
山梨県富士山世界文化遺産保存活用推進協議会などが、富士山の大切さについて学ぶ「キッズ・スタディ・プログラム」を授業で活用してもらおうと、授業用教材セットを作成。葛飾北斎の「冨嶽三十六景」などの浮世絵を使って江戸時代に栄…
松尾芭蕉は1682(天和2)年の江戸の大火で芭蕉庵を焼け出され、門人の一人で谷村城家老・高山伝右衛門=俳号麋塒(びじ)=を頼って、約半年間山梨県都留市に滞在したとされる。 市内には現在芭蕉の句碑が多く、東漸寺、円通院…
日本郵便は笛吹市の新道峠展望デッキ「FUJIYAMA ツインテラス」をテーマにしたフォトコンテスト入賞作品のオリジナルフレーム切手を作った。市内外の15郵便局で販売している。 コンテストは全国から167点の応募があり…
富士山の世界文化遺産登録活動や観光キャンペーンと連携し、地場産品のブランド化を一層推進するために開発された「富士山ブランド・ロゴマーク」。日本のシンボル・富士山をデザインしたロゴマークを製品に表示してもらうことで、県内…
富士吉田 川魚、香物メニュー再現 富士講信者の宿坊だった御師の家で提供されていた御師料理を継承しようと、富士吉田市内の御師らは26日、富士吉田市上吉田4丁目の上文司家で御師料理のお披露目会を開いた。 市関係者を招き、…
山梨県鳴沢村の特産品サツマイモの切り干し(干しイモ)。切り干し作りのために栽培している品種「玉豊」と、強い甘みが特徴の「ベニハルカ」や「シルクスート」などを使用。 切り干し作りにはまず、サツマイモを収穫後1カ月ほど保存…
観光客 早期に「帰宅」 山梨、静岡、神奈川3県などでつくる富士山火山防災対策協議会は3月29日、噴火に備えた避難基本計画を改定し、最終報告として公表した。登山者を含む観光客のほか、医療機関や福祉施設を利用する要支援者の…
山梨県富士河口湖町大石地区で栽培されている大和芋。富士山の恵みを受けて育つ“富士山やさい”の代表格のひとつ。 同地区は富士山の火山灰と御坂山系の肥沃な土が混じり、2~3メートル掘っても石が出てこないので根菜作りに最適…
富士河口湖 家族連れ祭り楽しむ 富士河口湖町観光連盟は25日、同町の大池公園でほうとう祭りを開いた。ほうとうの普及が目的で、家族連れなどに無料で提供した。 町内でほうとう専門店を展開する歩成からの提案を受け、連盟が初…
安全な富士山のPRも 第4回富士山安全対策連絡協議会(会長・石原茂富士吉田市長)は20日、富士吉田市民会館で開き、ことしの夏の富士山安全対策を最終的に協議した。その結果(1)登山道(県道)の一部変更に伴う改修工事(2)…
大月でキャンペーン JR東日本八王子支社は大月市観光協会と連携し、31日まで観光客にオリジナルポストカードを配布するキャンペーン「富士山いくなら、大月よってけし!」を展開している。 観光協会などで扱う「大月市体験ガイ…
大正期に興った「新版画運動」の重要な担い手であった川瀬巴水(1883-1957年)は、東京市芝区(現・東京都港区)に糸組物職人の長男として生まれた。幼少から絵を描くことを好み、一時は周囲の反対もあって画家への道を断念す…
山中湖にグランピング施設 情報通信サービス業などを手掛けるビジョン(東京)は、山中湖村山中にグランピング施設「VISION GLAMPING Resort&Spa 山中湖」をオープンした。 施設は山中湖花の都公園の南…
県センター 駆除へ生態調査 県水産技術センターは24日、富士河口湖町と身延町にまたがる本栖湖で昨年11月に初めて生息が確認された大型外来マス「レイクトラウト」の生息実態調査と、駆除の様子を報道機関に公開した。 センタ…
山梨県富士吉田市が、富士山の眺望スポットとして人気の新倉山浅間公園(同市新倉)に設置した、晴れた日の眺めを写した看板。富士山が雲に隠れても、眺めの良さが分かるようにと企画。公園周辺の道路には道順の案内板も増やし、観光客…
山梨県鳴沢村が原産とされ、富士北麓地域を中心に採種と栽培が繰り返されてきた鳴沢菜。その歴史は古く江戸時代までさかのぼると伝えられ、野沢菜や広島菜などと並ぶ、いわゆる「地菜」として地元で大切に育てられている。 もともと…
山梨市で合同写真展 山梨市文化協会写真部と甲州市文化協会塩山支部写真部による合同展が23日、山梨市民会館で始まった。 両写真部のメンバー24人が撮影した作品47点を展示。富士吉田市や精進湖から撮影した富士山や鳥、花、…
「忍草の暴れみこし」の異名を持つ山梨県忍野村忍草の「忍草諏訪神社秋の例大祭」。毎年9月19、20日に開かれ、長さ5メートルを超す大きなみこしが威勢よく練り歩く。 みこしは初日、忍野八海の「湧池」で清められた後、神社を出…
山梨県は23日、忍野村を流れる新名庄川を対象とした浸水想定区域図を公表した。「千年に1度起こりうる最大規模の雨」が降り、浸水した場合の水深(最大20メートル未満)を5段階で判定。忍野八海がある下流域が深くなりやすく、場…
【登山回数】「初めて登る」が半数 県内在住者は1.5% 富士登山の回数を尋ねたところ、約半数の47.0%が1回目と回答。例年同様、初めて登る人が多い傾向が示された。2回目が22.5%、3回目が7.5%と続いた。 …
推進協 世界遺産登録10年で 県富士山世界文化遺産保存活用推進協議会が8日、静岡県富士市内で開かれ、6月に富士山の世界文化遺産登録から10年を迎えることから、公式ガイドブックのデジタル化など普及啓発を強化していくことを…
第33回富士忍野グランプリフォトコンテスト(忍野村主催)の入選作品が決まった。 四季を通じて村から撮影された富士山をテーマに募集。県内外から599点の応募があった。村は3月下旬に表彰式を行い、同村の岡田紅陽写真美術館…
富士山の美化に若者の力を生かそうと2000(平成12)年、山梨県ボランティアセンターで活動する高校生と特定非営利活動法人山梨県ボランティア協会が中心となり発足したボランティアグループ「子富士の会」。公益財団法人「富士山…
山梨県富士河口湖町が2016年4月、同町勝山の羽根子山北側の斜面に散策路を整備。新しい散策路は従来の山頂につながる道より勾配が緩やかで、高齢者や子どもが安全に登ることができる。山頂を富士山と河口湖が望めるスポットとして…
富士吉田市が抽選会 富士吉田市は6日、7月に富士山を舞台に開かれる「第76回富士登山競走」のふるさと納税枠の出場者を決める抽選会を開いた。 2月18日~3月3日に特設サイトからふるさと納税で5千円以上寄付した希望者の…
7月開業 バイク型疾走感抜群 富士急行(富士吉田市新西原5丁目、堀内光一郎社長)は14日、富士急ハイランドに新規の大型コースターを7月に開業させると発表した。 同社によると、新コースターはバイクに乗るような姿勢で乗車…
山梨県の道志村を象徴する、清流として知られる道志川。山中湖の東北端、村南西部の山伏峠が水源。東北端の神奈川県境まで21.8キロ。標高差は1190メートルから350メートルと840メートルもあり、下流では道志渓谷の景観美…
山梨日日新聞と静岡新聞は富士山臨時支局開設に合わせ、富士山の安全対策などに関するアンケートを登山者200人を対象に行った。 落石や転倒などから身を守る対策として推奨されているヘルメットなどの装備を着用・携行した人は6…